動物や昆虫、机等の同じものを指す時は脚と言う漢字を主に使い、ヒトのそれを指す時は余り区別無く足と脚を使う!
肢と言う漢字は「体から分かれる枝」と言う意味で器質的、生物的に使われる事が多い!
例として四肢と書き対の手と脚を指す!
上肢、下肢と書いて手足を指す等!
腿と言う漢字は太ももや脹脛(フクラハギ)を指し、上腿(ジョウタイ)と書き下肢の膝から上を指し、下腿(カタイ)と書き下肢の膝から先を指す!
又、大腿(ダイタイ)と書きモモを指し、小腿(ショウタイ)と書きふくらはぎを指す!
日本語で足は、ソクと読んで、対となる具足の数を数える場合に用いる時がある!
例として靴下や靴等を「一足、二足(イッソク、ニソク)」と数える!
日本語で足は、移動手段として使う事がある!
移動手段が無いと言う意味で「足が無い」!
日本語で足は、歩行や進行の状態を指して使う事がある!
例として「足を止める」と表記して実際に歩く足を止めた状態を言ったり、その他手段を使った時の進行を止めた状態を言う! 同様の表現で、手を用いて「手を止める」と表記して進行中の作業を止める事を言う!
日本語で足は、行動範囲を示す言葉として使う事がある
日常の行動範囲を超え遠方に行く事を「足を伸ばす」!
日本語で足は、予定範囲のはみ出し部分を言う事がある!
「足が出る」と表記して予算を超過した状態を表す!
日本語で足は、モノの下部や下位を指して使う事がある!
一連の末尾や規定数以下を削ると言う意味で「足を切る」!
日本語で足は、好ましく無い経歴や過去からの脱却の行為を指して使う事がある!
「足を洗う」!
日本語で足は、本数に限らず接地する部分を指して使う事がある!
建造物の足、家具の足、椅子の足!
又、支柱が一つ以上になる事によって「足」と表現する頻度が上がる!
日本語で足を、「あんよ」「大御足(おみあし)」等と表現する事がある!
日本語で足は、脚の部分を含んで「あし」と使う場合があり、表記に限らずその区分は明確に分けられていない事もある!
趾の数え方は拇指側から第I趾、第II趾、…と呼び、足の親指つまり第I趾を母趾とも呼ぶ!
日本語で足は、物体が持つ肢を指すのに、適当な言葉が無い時に用いる事がある!
「げじげじの足」!
日本語では烏賊の足の部分に限って「ゲソ」と呼んでおり、それを網焼き等にして火に炙った物を食べる!
中国では足と言う表記を使わず、脚と言う漢字を採用している!
~今回のブログは「足」!と「脚」!について!~
・・・形態学的に人の足は踝(クルブシ)辺りから末梢端接地部迄を指して呼んでいる(foot)。
人のそれに限らず末梢端を「爪先(ツマサキ)」、趾表体部上面を「足の甲」、裏体部を「足の裏」又は「蹠(あしうら)」「足底(ソクテイ)」「あなひら(趺=足のひら)」、表裏部下端を「踵(かかと)」「きびす」と呼ぶ。
人間の場合、爪先には手と同様に5本の指(足指、趾)がある。医学用語としては、体の内側から第1趾 - 第5趾と数字で呼び、日本語の俗語では屡(しばしば)手と同じく親指・人差指・中指・薬指・小指と言う。一般に、第1趾(親指)が最も太く、第2趾(人差指)が最も長く、第5趾(小指)が最も細くて短い。足の指は、手の指に比べて非常に短く、手の指程自由には動かせない。退化すれば、小指が無くなる、とも言われている。
指の先には爪がある。日本語の「爪先」は、本来は「爪の先」の意味であるが、手(の指)の先については「指先」と言い、「爪先」は足についてのみ言う。
爪先は、歩行の際に重要な役割を持つ。但し、第五指(小指)は、失ってもそれ程足取りに影響を及ぼさない。

西洋では、悪魔にはかかとは無いとされている。殆どの哺乳類では、かかとに当たる部分は歩く際に地上に着かない。アライグマ等、かかとを地上につける動物もあるが、これは、二足で立ち上がる際の安定性を増す効果がある。但し、人のかかとの様に目立たない。これは、ヒトではかかとが肥厚していると同時に、土踏まずがある為にかかとが突出しているからである。これは、ヒトが直立二足歩行をする為に発達した構造と考えられる。
かかとは人体の中でも硬い部位なので、格闘技等では打撃にこの部位を用いる例もある。但し、かかとより爪先の方が先に出ているし、前蹴りならば指先か指を挙げた足裏の先端部を使う事が多く、かかとは方向性的に使い易いとは言えない。特にかかとを使う例としてはかかと落とし等が良く知られる。
足の指を手の指と区別して「趾(あしゆび)」と呼ぶ事もある。 又、接地部より上に向かうに当たって足首、脛(すね)、膝、腿(たい、もも)と言った部位に分けられており、脚と比べて頻度は低いが腿迄を含み足と呼ぶ事がある。

Copyright(C)2014/倭整体所の日々雑感 All Rights Reserved.
又、便宜上、同じ訓を持つ「脚」と言う漢字を当て腿以下の下肢全体を指して呼ぶ事がある。

便宜上、日本語で同じ音を持つ「足」と言う漢字を当て、踝以下接地部を指して区別の為に使い分けて呼ぶ。
脚と同じ部位を指して腿(タイ)と言う表記を用いる事もあり、腿と言う字自身は太ももや脹脛(フクラハギ)![クリックすると新しいウィンドウで開きます]() を指すが、上腿(ジョウタイ)と書いて下肢の膝から上を指し、下腿(カタイ)と書いて下肢の膝から先を指す。
を指すが、上腿(ジョウタイ)と書いて下肢の膝から上を指し、下腿(カタイ)と書いて下肢の膝から先を指す。
 を指すが、上腿(ジョウタイ)と書いて下肢の膝から上を指し、下腿(カタイ)と書いて下肢の膝から先を指す。
を指すが、上腿(ジョウタイ)と書いて下肢の膝から上を指し、下腿(カタイ)と書いて下肢の膝から先を指す。 又、大腿(ダイタイ)と書いてモモ![]() を指し、小腿(ショウタイ)と書いて脹脛を指す。
を指し、小腿(ショウタイ)と書いて脹脛を指す。
.jpg) を指し、小腿(ショウタイ)と書いて脹脛を指す。
を指し、小腿(ショウタイ)と書いて脹脛を指す。 一般的に脚は身体全体の重さを直接的に引き受ける部位であり、全身中最も太い骨と、瞬発力と持久力を兼ね備えた筋力を備える。
脚の筋肉は骨格筋によって構成され、大きく大腿筋、下腿筋、足筋に分けられ、それ等と骨を繋ぐ腱とで脚の動きを調節している。
通常は歩行には用いられず、地面に着かない。
日常生活において腕で体重を支える事は無い為、腕の筋力は脚のそれには及ばない。
イヌの「お手」等、他の生物の類似箇所を指して概念的に同様の呼び方をする場合があるが、生物によってその構成は大きく変化しており、前脚を腕と一概に呼ぶ事は出来無い。

「もも」は古くは「はぎ」と言い、対面して向かい合う部分を「向かはぎ」と呼んだが、やがて「はぎ」は脹脛(ふくらはぎ)を指す様になり、「向かはぎ」は「向こう脛(むこうずね)」に変わった。
即ち向こう脛は「脛」と同義である。
脹脛は「腓(こむら)」とも呼ばれる。
「(足が)攣(つ)る」とも言われる。
に起こり易い為、腓腹筋痙攣と同義と見做す事もある。
こむら返りを生じている筋は硬く収縮しており、局所の筋が硬く膨隆しているのが分かる。
特に睡眠中は眠気が吹き飛ぶ程の激痛が襲うものの、寝起きで早急に対処が出来無い為、起床後に脹脛(ふくらはぎ)の筋肉痛や寝不足が残る事がある。
健常人でも起こる事があるが、様々な骨格筋に頻回に繰り返したりする場合は病的なものと考える。
脱水(発汗、下痢、利尿薬の服用)又は電解質代謝異常(Ca、Mg)、腎不全、血液透析、甲状腺機能低下症、妊娠、脊髄性筋萎縮症や多発神経炎等の神経原性筋萎縮をきたす疾患、下肢静脈瘤、特殊な例(McArdle病、里吉病等)等で頻発する事が多いので、その様な疾患を鑑別に挙げる必要がある。

膝の裏は凹んでいて、「膝窩(しっか)」![]() 「膕(ひかがみ)」等と呼ばれる。
「膕(ひかがみ)」等と呼ばれる。
 「膕(ひかがみ)」等と呼ばれる。
「膕(ひかがみ)」等と呼ばれる。 又、足の成長は、男性が16歳頃、女性は14歳頃で止まり、女性の足は男性の足と比べて小さい。
膝は足裏以外では接地する事が多い部位である。例えばかかとを挙げ、つま先と膝をついて座る座り方は「跪く」と言い、多くの民族に見られる。つま先を伸ばして足の甲と膝をつくのを正座と言う。何れも改まった場、或いは遜(へりくだ)った姿勢を示す。這う場合も足裏では無く膝をつく。転ぶ場合には膝からぶつかる事も多い。
膝の関節は、「大腿骨と脛骨で作られる関節」と、「大腿骨と膝蓋骨で作られる関節」とで形成される。![ファイル:膝の内部構造(右内側).PNG]() この内、大腿骨と脛骨で作られる関節は螺旋関節と言われる1軸性の関節形態を成している。膝関節は、腕における肘関節
この内、大腿骨と脛骨で作られる関節は螺旋関節と言われる1軸性の関節形態を成している。膝関節は、腕における肘関節![クリックすると新しいウィンドウで開きます]() に対応する。
に対応する。
 この内、大腿骨と脛骨で作られる関節は螺旋関節と言われる1軸性の関節形態を成している。膝関節は、腕における肘関節
この内、大腿骨と脛骨で作られる関節は螺旋関節と言われる1軸性の関節形態を成している。膝関節は、腕における肘関節 に対応する。
に対応する。日本語で膝と言う場合は、膝頭の上部の大腿部(もも)の前面を含める事がある。欧米の言語には、大腿部前面の座った時に水平になる部分を指す言葉(ラップ等)があるが、日本語にはそれに一対一に対応する言葉は無く、通常は「膝」と言う。
膝枕は膝頭では無く腿を枕の様にする事である。腿の上(lap top)に乗せて使うラップトップパソコンは、日本語では「膝上パソコン」と訳された。コンピュータは大きさによって大まかにデスクトップ(卓上型)、ラップトップ(膝上)、パームトップ(掌上)に分類され、「ラップトップ」の名称は椅子に座りながら「膝の上(ラップトップ)でも使用出来る」との意味からで、英語の範疇では主に和製英語である「ノートパソコン」を含めたカテゴリーである。但し日本では通常「一般的なノートパソコンよりも一回り大きいカテゴリー」として使われている。
膝は体重を支える重要な部位だが、負傷するケースも多い。膝が伸びた状態で正面からの衝撃に弱く、体重が過度に重いと膝に負担がかかり障害を起こす。半月板や前十字靭帯の負傷、傷害のケースは多く、腰に次いで直立二足歩行の弊害を大きく受けている箇所である。
又、横に捻る動作に全く対応していない。格闘技で使用される関節技でヒールホールド![]() (C)YOSHIKURA DESIGN,LTD. 2003-2009. All right reserved.GBRと言うかかとを捻る技があるが、この技は膝靭帯を破壊する危険な技である。
(C)YOSHIKURA DESIGN,LTD. 2003-2009. All right reserved.GBRと言うかかとを捻る技があるが、この技は膝靭帯を破壊する危険な技である。
 (C)YOSHIKURA DESIGN,LTD. 2003-2009. All right reserved.GBRと言うかかとを捻る技があるが、この技は膝靭帯を破壊する危険な技である。
(C)YOSHIKURA DESIGN,LTD. 2003-2009. All right reserved.GBRと言うかかとを捻る技があるが、この技は膝靭帯を破壊する危険な技である。その反面、膝蹴りは重くて硬く、使用頻度が高い。

「裸足」と「素足」ってどう違うのかっつーと、裸足は靴下等履かずに地面に直接触れてる足![クリックすると新しいウィンドウで開きます]() で、素足は、靴下等履かない所迄は一緒だけど、靴や草履を履いてる
で、素足は、靴下等履かない所迄は一緒だけど、靴や草履を履いてる![クリックすると新しいウィンドウで開きます]() のが違う所。
のが違う所。
 で、素足は、靴下等履かない所迄は一緒だけど、靴や草履を履いてる
で、素足は、靴下等履かない所迄は一緒だけど、靴や草履を履いてる のが違う所。
のが違う所。 石田純一は「裸足に靴を履いてる」のじゃなくて「素足に靴を履いてる」事となるので。

足は時として第二の心臓とも呼ばれ、立位時重力に従って下方向へ体液が流動する事によって引き起こされる体液停滞むくみ(浮腫(ふしゅ)とは、顔や手足等の末端が体内の水分により痛みを伴わない形で腫れる症候。細胞組織の液体<細胞間質液>と血液の圧力バランスが崩れ、細胞組織に水分が溜まって腫れる)を、足の血管周辺の筋肉の運動によって上部へ押し返し再び循環系に戻す事を行っている。
又、手と同様に中医学における経絡(ツボ)が多くある![]() とされ、又、足の不具合が体の他の部位の様々な病因となる事があるとされる。
とされ、又、足の不具合が体の他の部位の様々な病因となる事があるとされる。
 とされ、又、足の不具合が体の他の部位の様々な病因となる事があるとされる。
とされ、又、足の不具合が体の他の部位の様々な病因となる事があるとされる。 又、足には手と同様に利き足があり、反対側よりも筋力、長さ等が発達している事が多く、左右の不均等が全身の歪みを引き起こすとも言われている。
この足の利きの違いが山中での遭難の原因輪形彷徨リングワンダリングを引き起こすと言われている。
足に何らかの症状を引き起こす病気として以下の様なものがある。

遺伝的な因子や骨折、脱臼(関節とは骨と骨の連結部分であり、骨と骨が向かい合っている面がある。この面が位置関係が本来の状態からずれた状態・関節を構成する骨同士の関節面が正しい位置関係を失っている状態。![]() 尚、関節部の損傷を示す言葉の一つに捻挫があるが、これは関節包や靭帯
尚、関節部の損傷を示す言葉の一つに捻挫があるが、これは関節包や靭帯![]() の損傷を指す用語であり、骨の位置関係の異常を指すものでは無い。関節に関節の許容範囲を超えた動きが与えられた為に起きる
の損傷を指す用語であり、骨の位置関係の異常を指すものでは無い。関節に関節の許容範囲を超えた動きが与えられた為に起きる![クリックすると新しいウィンドウで開きます]() 損傷の一つが捻挫である。多くは患部に痛みと腫脹、熱感を伴う)、靭帯損傷、筋麻痺等に加え、最も多いとされるのが成長期に長時間立ち続ける事によって起きる静力学的扁平足である。
損傷の一つが捻挫である。多くは患部に痛みと腫脹、熱感を伴う)、靭帯損傷、筋麻痺等に加え、最も多いとされるのが成長期に長時間立ち続ける事によって起きる静力学的扁平足である。
 尚、関節部の損傷を示す言葉の一つに捻挫があるが、これは関節包や靭帯
尚、関節部の損傷を示す言葉の一つに捻挫があるが、これは関節包や靭帯 の損傷を指す用語であり、骨の位置関係の異常を指すものでは無い。関節に関節の許容範囲を超えた動きが与えられた為に起きる
の損傷を指す用語であり、骨の位置関係の異常を指すものでは無い。関節に関節の許容範囲を超えた動きが与えられた為に起きる 損傷の一つが捻挫である。多くは患部に痛みと腫脹、熱感を伴う)、靭帯損傷、筋麻痺等に加え、最も多いとされるのが成長期に長時間立ち続ける事によって起きる静力学的扁平足である。
損傷の一つが捻挫である。多くは患部に痛みと腫脹、熱感を伴う)、靭帯損傷、筋麻痺等に加え、最も多いとされるのが成長期に長時間立ち続ける事によって起きる静力学的扁平足である。 乳幼児の頃の偏平足は一般的に見られる状態であり、病気と言えるものは後天的なものを指し、土踏まずを鍛える運動や矯正装具等で治療する事が出来る。

外反母趾は足の親指が骨を基盤として小指の方向に曲がって行く器質的な病気で、体重が変わり易く靭帯が緩む中年以降や足に合わない靴を履く人に多く発生し、先端部の細いハイヒール等を履く女性に発現が多いとされる。
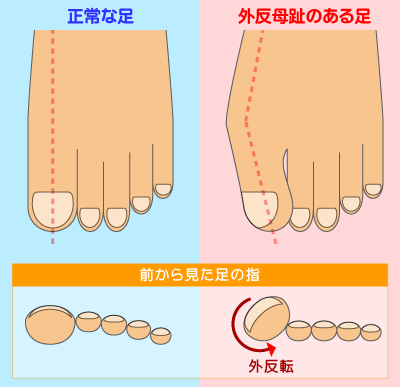
多くが生まれついての病気に分類されるが内反足は男の子に多く早期発見、治療、矯正が大切な足の異常形態である。

対して外反足は自然治癒が見込めるとされる。
をガツーン!とぶっつけてギャアアーッ!と痛くなって・・・そいで以て今現在も微妙に痛い状態の辛抱しんちゃん。
そんな足について調べたのが今回のブログでした。
 に相当する。
に相当する。 の向こう脛側には、皮下の直ぐ下の骨膜上を神経が走っている(
の向こう脛側には、皮下の直ぐ下の骨膜上を神経が走っている( とは、腓(こむら) =
とは、腓(こむら) = 
 と
と から成り立っており、立位時の体重移動にそれぞれが細かく動く事で負荷を分散させる事に役立っている。
から成り立っており、立位時の体重移動にそれぞれが細かく動く事で負荷を分散させる事に役立っている。 と言う。
と言う。