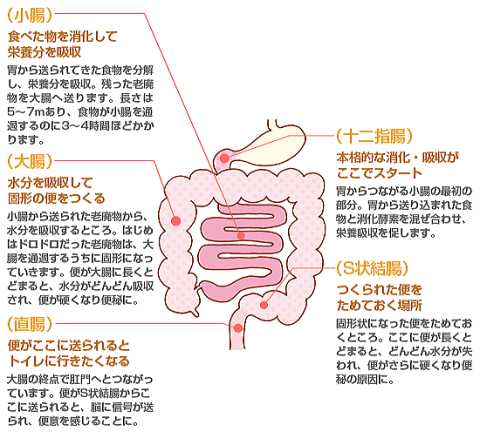
いや~汚い話だが、下痢で苦しい。
まあ、辛抱しんちゃんのブログは、高尚(?)な話題から下種な話題迄ゴッチャに話題を取り上げる・・・皆平等に取り上げているので、今回も邪険にせず取り上げてみたい・・・

軟便(なんべん)、泥状便(でいじょうべん)、水様便(すいようべん)とも言う。

東洋医学では泄瀉(泄は大便が希薄で、出たり止まったりする事。瀉は水が注ぐ様に一直線に下る)とも呼ばれる。
それ等の生物は、消化器官の作りが原始的であったり、全排泄(出産や産卵をも含む)を総排泄腔(直腸・排尿口・生殖口を兼ねる器官。総排出腔を持つ動物では、消化管<腸管>の末端である糞管<肛門管>、泌尿器からの輸尿管、生殖器からの生殖輸管<卵管・精管>の全てが、共通の室<腔部>である総排出腔に開口する)で行う事から、便の柔らかい事が常態なのである。
2004年には世界で約25億人が下痢に罹患し、150万人の5歳以下の子供が死んでいる。
これ等の患者の半分以上がアフリカ及び南アジアに在住している。
20年前には500万人に1人が毎年死亡していたが現在では改善しつつある。
これ等の年代では、下痢の死因は全体の16%を占め、肺炎の17%の死因に次いで第2位の死因となっている。

何等かの原因で水分を多分に残したまま便意を催して排便される事がある。
これが下痢である。
大人は乳糖分解酵素の活性が失われ、乳糖を分解、吸収出来無い為大腸内での乳糖の濃度が高まると大腸内の浸透圧も高まり、大腸内で多量の水分を保留する事となり、これが下痢を引き起こす。
多くの場合、消化不良や下痢等の症状を呈する。
結果、腸管の中に乳糖が残ってしまう事で乳糖不耐症の諸症状が発生する。
これは健康であっても、哺乳類であれば起こり得る現象である。
つまり、乳糖不耐症の根本的な原因は哺乳類の性質だからと言う事も出来る。
このラクターゼの分泌が少ない個体に、乳糖の不耐が発生する。
但し、ヒトの乳糖不耐症者の場合、ラクターゼが全く存在しない場合もあれば、存在しても十分量が無いだけの場合もあるので、一口に乳糖不耐症と言っても、乳糖の許容量には個体差が見られる。
この為に、乳糖に対する不耐が起こっていたとしても、乳糖を含む食品の摂取量が十分に少ない為に、自覚症状が無い者もいる。
この乳糖不耐による自覚症状が無い者も含めて、ラクターゼの活性の低下が見られる場合は乳糖不耐症としてカウントし、乳糖(主に牛乳の摂取)の有害性を主張する例も見られる。
然し、自覚症状が無い場合は、常識的な量を摂取している限り、健康上の問題は生じないとされる。
乳糖不耐症は、小腸にラクターゼが存在しないか、存在しても十分で無い為に、乳糖を分解出来無い、又は、十分に分解出来無い事が原因で起こる。
乳糖は二糖類の1種であり、このままでは吸収する事が出来無い。
乳糖不耐では屡(しばしば)下痢が発生する。
すると腸壁から水分が染み出し、便が軟化して浸透圧性下痢が発生するのである。
更に、腸管内に住む微生物には乳糖を利用する事の出来る種類もいて、その働きによって、乳酸や二酸化炭素が発生する。 これ等の酸により便のpHが6を下回ると、大腸を刺激して、その蠕動運動を強めてしまう事も下痢の原因となる。
又、腸管内で発生した二酸化炭素等は気体となる為、腹部膨満を感じる場合もある。
これ等の「下痢」の挙動は狭義のオリゴ糖(難消化性)を摂取した時と同一であるが、こち等では「腸内環境の改善」と表現される事が多い。
エリスリトールは体内に吸収されるので下痢が起き難い。
大量のマグネシウムの摂取も人体に大量に吸収されない為同様のメカニズムにより下痢が引き起こされる。
下痢になる原因として
食べ過ぎによる消化不良
早食いによる消化不良
就寝前に食事をした場合による消化不良
腐敗した物を食べた事に寄る食中毒
冷たい物の飲み過ぎや食べ過ぎ
飲酒した日の翌朝
早朝からの冷えた飲料の摂取
腹を冷やしたり、食後にベルトを締め付け過ぎた時等
乳糖不耐症の者が牛乳の様な乳糖を含む食品を多量に摂取した場合
人工甘味料を大量に摂取した場合
油を大量に摂取した場合
マグネシウムを過剰に摂取(マグネシウムを豊富に含む豆乳を大量摂取、マグネシウムを多く含む薬剤を摂取)した場合
外国で日常食べ慣れない物を多量に摂取した
O157(腸管出血性大腸菌:enterohemorrhagic Escherichia coli<EHEC>の、O抗原が157番の大腸菌)、アメーバ赤痢、ノロウイルス 、ロタウイルス、アデノウイルス等の細菌やウイルスに経口感染して起こる食中毒 過度の精神的ストレス
、ロタウイルス、アデノウイルス等の細菌やウイルスに経口感染して起こる食中毒 過度の精神的ストレス
が挙げられる。
急性のものと慢性のものに大まか分けられる。
発症から二週間以内のものを大体急性のものとして扱う。
ウイルス性のものである可能性が高い。
殆どの場合、自然に治癒する。
便が非常に柔らかくなる以外の主な症状としては、
虚血は、動脈血量の減少による局所の貧血。
阻血に同義。
乏血或いは全身性の貧血(一般的に貧血と呼ばれる現象)と区別して局所性貧血と呼ばれる事もある。
虚血が持続すると細胞の変性、萎縮、線維化が生じる。
虚血では血流が完全に遮断される為に解糖の基質の供給が妨げられる為、虚血に陥っている臓器では解糖の基質の枯渇により細胞内代謝物の蓄積が生じる。
等が挙げられる。
特に大腸での水分吸収が行われない為に生じる脱水症状は危険である。
一定の水素イオン指数ことpotential hydrogen:pH (7.4) に
なる様に保たれている。
平衡を酸性側にしようとする状態をアシドーシス
平衡を塩基性側にしようとする状態をアルカローシスと言う。
7.4より上になった(上昇した)状態をアルカレミアと言う。
共に全身の細胞にとっての環境の異常であり
高度なものでは呼吸抑制から死に至る事もあると共に
重篤な疾患の結果として生じる為治療の指標になる。
このpHの測定は血液ガス分析
によって成される。
下痢の際には通常より多くの水分が失われる為、それを補填する為に多目の水分補給が必要である。
浸透圧の問題と、ナトリウムの吸収経路の問題(ナトリウムのトランスポーターはグルコースと共輸送のものがある為)から、家庭では、温かい「極薄い」味噌汁やスポーツドリンク等を小まめに少しずつ取ると良いと言われる。

脱水症状は重篤になる事もある為、水分補給は気をつけて行う必要がある。
食事を取らない場合は、一日2000mLを目安に少しずつ飲むと良い。
尿量が「何時もくらい出る」と言うのも一つの目安になる。
東洋医学に寄ると、冷やした飲み物は望ましく無いとされている。
西洋医学においても、冷たい飲み物は胃腸に刺激になる為、避けた方うがいいと考えられる。
何時もの下痢が突然起きた場合には、下痢止め薬を服用すると良い。
梅干等も効果があるとされている。
食中毒等の感染症に伴う下痢は、病原体を速やかに排出する防衛作用であり、無闇な下痢止め処置はかえって病状の悪化を招く為、服用すべきで無い。
「何時もの下痢」でも異常に下痢が続く場合や症状が急変した場合は直ぐに医師に相談すべきである。
予防も含め、東洋では下痢に対しては腹部を冷やさない様にする事が大切であるとされている。
不快感を軽減する事も出来る為使い捨てカイロ(鉄粉の酸化作用を利用したカイロであり、不織布や紙の袋に空気中で酸化発熱する鉄粉を入れた物が一般的である。その他、通常触媒として鉄の酸化を速める食塩とそれを保持する高分子吸水剤、酸素を取り込む為の活性炭、鉄の錆びを促進する水、水を保水する為のバーミキュライト<農業や園芸に使われる土壌改良用の土。蛭石を800℃程で加熱風化処理し、10倍以上に膨張させた物>が入れられている。安価で簡便な事等から現在カイロの主流となっている)の様な発熱体を腹部にあてがう事も役に立つ。
ファッションの趣味として、腹部を露出する事を好む者の場合、下痢になるリスクが高い為飲食物に注意を払うのが望ましい。
尚、同じ腹痛でも、虫垂炎等の炎症が原因の場合、温める事は逆効果となるので注意を要する。
重篤な疾患で無いと診断されていても、慢性に下痢をしてしまう人は、カフェイン等腸を必要以上に刺激してしまう物を避け、高浸透圧の人工甘味料も避けるべきである。
水に溶かす前の状態の物を経口補水塩(Oral Rehydration Salts)と言う。
・・・まー、兎に角下痢で辛い。
辛いのよ。
単なる腹痛と思わないで欲しいな。
一歩間違えたら脱水等で死ぬ事もある下痢。
トイレにずううっと籠ってウーンと唸りながらドドドドと出すのを只管待ち、出た後は暫く座って残りを出す・・・何とも辛い。
単にアイス食ったから下痢になったとかじゃ無くて、ちゃあんと医学的な事情が以上挙げた様に盛り沢山ある為、下痢と言っても馬鹿にはしてはいけないよ!

臭いやら汚いやらのイメージが先走るが、内実はキッツイ体の不調なので、体を労わる事を大事にしましょうね。