三十二相八十種好(さんじゅうにそうはちじっしゅこう)とは、仏の身体に備わっている特徴。

見て直ぐに分かる三十二相と、微細な特徴である八十種好を併せたもの。
「相」と「好」をとって相好とも言う。
相好は又、転じて、顔形・表情の事。
その八十種好の中に
「福耳:耳が肩迄垂れ下がっている」と
「耳朶環状:
耳たぶに穴が空いている」
について設定されている。
今回のブログは、この三十二相八十種好の八十種好の内「福耳」「耳朶環状」に係わる・・・耳たぶについて綴る。

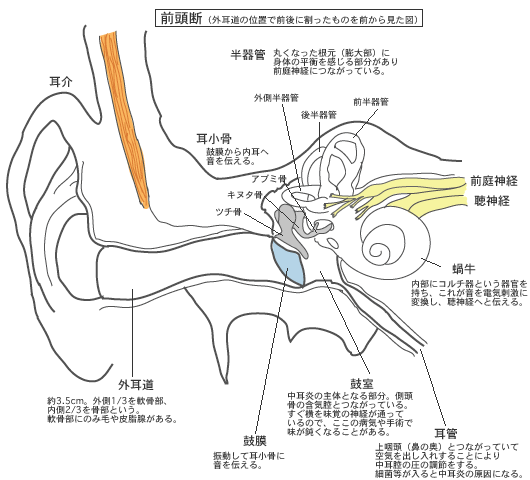
耳朶(じだ)、耳垂(じすい)、耳たぼ(みみたぼ)とも言う。
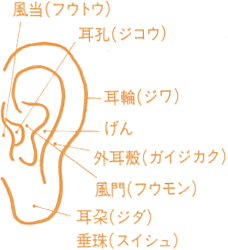
外耳(がいじ)とは、耳の構造の内耳介(耳殻)と外耳道を合わせた部分。
一般的な言葉で言うと(外から見える)耳と耳の穴の事。

ヒト以外の動物では集音効果のある物が多く、随意運動が可能である種も多い。
ヒトにおいては集音効果は乏しく、耳介を動かす筋も発達していない(耳介を動かす事が出来る人もいる)。
尚、耳たぶは耳介に含まれる。
外耳道(がいじどう)は、所謂耳の穴の事。
骨部は毛が生えておらず、軟骨部は毛が生えており皮脂腺等もある。
三叉神経(さんさしんけい)は、12対ある脳神経の一つであり、第V脳神経(CN V)とも呼ばれる。

迷走神経(めいそうしんけい)は、12対ある脳神経の一つであり、第X脳神経とも呼ばれる。
迷走神経は脳神経の中で唯一腹部に迄到達する神経である。
迷走神経は体で一番重要な神経であると言える。
外耳道の内側(奥側)を触ると咳が出るのはその為である。

ヒトの耳たぶの付き方の類型には、頭部から離れて垂れ下がる形となる分離型と、頭部となだらかに繋がった輪郭を描く密着型とがある。
ゲノムと言う語には、現在、大きく分けて二つの解釈がある。
古典的遺伝学の立場からは
二倍体生物におけるゲノムは生殖細胞に含まれる染色体
若しくは遺伝子全体を指し
この為体細胞には2組のゲノムが存在すると考える。
一倍体生物においては
全遺伝情報を指す。
分子生物学の立場からは
全ての生物を一元的に扱いたいと言う考えに基づき
ゲノムはある生物の持つ全ての核酸上の遺伝情報としている。
但し、真核生物の場合は
細胞小器官(ミトコンドリア、葉緑体等)が持つ
ゲノムは独立に扱われる
(ヒトゲノムにヒトミトコンドリアのゲノムは含まれない)。
それ以外のノンコーディング領域に大別される。
ゲノム解読当初、ノンコーディング領域は
その一部が遺伝子発現調節等に関与する事が知られていたが
大部分は意味を持たないものと考えられ
ジャンクDNAとも呼ばれていた。
現在では遺伝子発現調節の他、RNA遺伝子等
生体機能に必須の情報がこの領域に多く含まれる事が
明らかにされている。
ヒトを始め2倍体の生物は、それぞれの遺伝子座について父母それぞれから由来した2つの対立遺伝子を持つ。
両親から同じ種類の遺伝子を引き継いでいる(両方の対立遺伝子に変異が無いか、対立遺伝子が両方とも同じ様に変異している)場合、ホモ接合と呼ばれ、異なる種類の遺伝子を引き継いでいる(片方の対立遺伝子が変異している)場合、ヘテロ接合と呼ばれる。
対立遺伝子の内、正常な(本来の)機能を有するものを野生型と言う。
変異を二種類に分けると、機能欠失型変異型と機能獲得型がある。
個体が持つ遺伝子の組合せを遺伝子型(ジェノタイプ)と呼ぶ。
これに対して、見かけ上現れる形質を表現型(フェノタイプ)と呼ぶ。
対立遺伝子には優性遺伝子・劣性遺伝子の区別をつける事が出来る場合が多い。
この場合、優性の形質を持つものを大文字 A、劣性の形質を持つものを小文字 a等の英字で表す。
優性遺伝子と劣性遺伝子がヘテロ接合している場合、優性遺伝子支配の形質が表現型となり、優性遺伝子のホモ接合の場合と同様となる(優性の法則)。

分離型で特に分厚く肉付きが良いものは東洋では福運があるとされる(福耳)。
福耳で最も良いと言われている形は、耳たぶが真下に垂れ下がらずその上に米粒が乗るぐらい口の方に向かっている相。
「釈迦」は釈迦牟尼(しゃかむに)の略である。
釈迦は彼の部族名若しくは国名で、牟尼は聖者・修行者の意味。
つまり釈迦牟尼は、「釈迦族の聖者」と言う意味の尊称である。
称号を加え、釈迦牟尼世尊、釈迦牟尼仏陀、釈迦牟尼仏、釈迦牟尼如来とも言う。
但し、これ等はあくまで仏教の視点からの呼称である。
僧侶等が釈迦を指す時は、略して釈尊(しゃくそん)又は釈迦尊、釈迦仏、釈迦如来と呼ぶ事が多い。

例えば、対立形質を持つ純系同士の交配では、子の代では1:0の割合で片方の性質が現れるが、これは見かけの事であって、劣性が遺伝していない訳では無い。
孫の代では3:1の割合で両者の性質が現れる。
オーストリアのブリュン(現在はチェコ領ブルノ)にあった修道院の司祭、グレゴール・ヨハン・メンデルが発見した。
現代の知識を以てこれを解釈すれば、大抵の場合、優性の性質はその種の普通の形質であり、劣性のものはそうでは無く特殊なものである例が多い。
これは、例えば一遺伝子一酵素説で考えれば分かり易い。
この説では、遺伝子は酵素の設計図であると見る。
その酵素が作れる事でその生物はある形質を発現出来る。
劣性の遺伝子はその設計図が壊れたものと考えれば良い。
その遺伝子を持つ生物はその酵素を作れないので、その形質を発現出来ず違った形になる。
これが劣性の形質である。
優性の遺伝子を持つ個体と劣性の遺伝子を持つ個体とが交配すれば、その子は優性遺伝子と劣性遺伝子をヘテロに持つ事になる。
その体内には正しい設計図と壊れた設計図が共存するので、正しい酵素と壊れた酵素が同時に作られる。
その結果、数が少なくはなっても正しい酵素が作られる事により、その形質は発現出来る事になるであろう。
つまり見掛け上は劣性の形質は出現しない。

耳飾り。
語源は ear + ring であるが、環状の物(耳輪)に限らずイヤリングと言う。
又、耳たぶ以外の耳介に挟む物もある(同、イヤーカフス/イヤーカフと呼称)。
デザインも様々であり、小さなリング状の物から、肩の近く迄垂れ下がる複雑なデザインの物迄ある。
重さと形状は、耳たぶとそこに開けた穴が、どれだけの重さに耐えられるかによって決まっている。
大き過ぎるデザインは行動の妨げになる他、他の物体との接触により引っ張られ、耳たぶを傷つける恐れがあるので注意が必要である。
多くの文化で身分や美しさの象徴として用いられている。
嘗ては、奴隷身分を示す為、耳から外す事の出来無いタイプの物が用いられていた所もある。
最近では、他の人の助けを借りなければ取り外す事の出来無い程複雑で巨大なタイプが流行している地域もある。
1 ヘリックス(Helix、耳輪上部)
2 インダストリアル (Industrial)
3 ルーク(Rook、対輪上部)
4 ダイス (Daith)
5 トラガス(Tragus、耳珠)
6 スナッグ(Snug、対輪中央部)
7 コンチ (Conch)
8 アンチトラガス(Anti-Tragus、対珠)
9 イヤーロブ(Ear Lobe、耳垂)
1、5、8、9は解剖学上の名称が
1、5、8、9は解剖学上の名称が
そのままピアスの部位の名称として使われている。
最も普及しているピアスの部位はイヤーロブである。

又、長期に渡って装着せずにいると、穴が塞がり再びピアシングをする必要が出て来る。
高熱のものをそれとは知らずに触った時等は、耳たぶを利用して冷却する事がある。
それは、耳たぶが人間の体の中で最も体温が低い部分であると言われる為である。
で!
「耳たぶ」の「たぶ」って何さ!?
・・・って思ったので調べてみました。

「耳たぶ」って、漢字で「耳朶」と書く。
「朶」は「垂らす」の意味なので、「耳を垂らす」意味から「耳朶」となった。
本当かどうか不明だが、太腿の事を「腿たぶ」と呼ぶ地方もあるらしい。
これも「耳たぶ」の「たぶ」と同義で使用されている。

・・・「たぶ」に関して気になるだけで遺伝とかピアスとかもオマケに調べてしまった。
「耳たぶ」っても、調べたら奥が深いですなあ・・・



